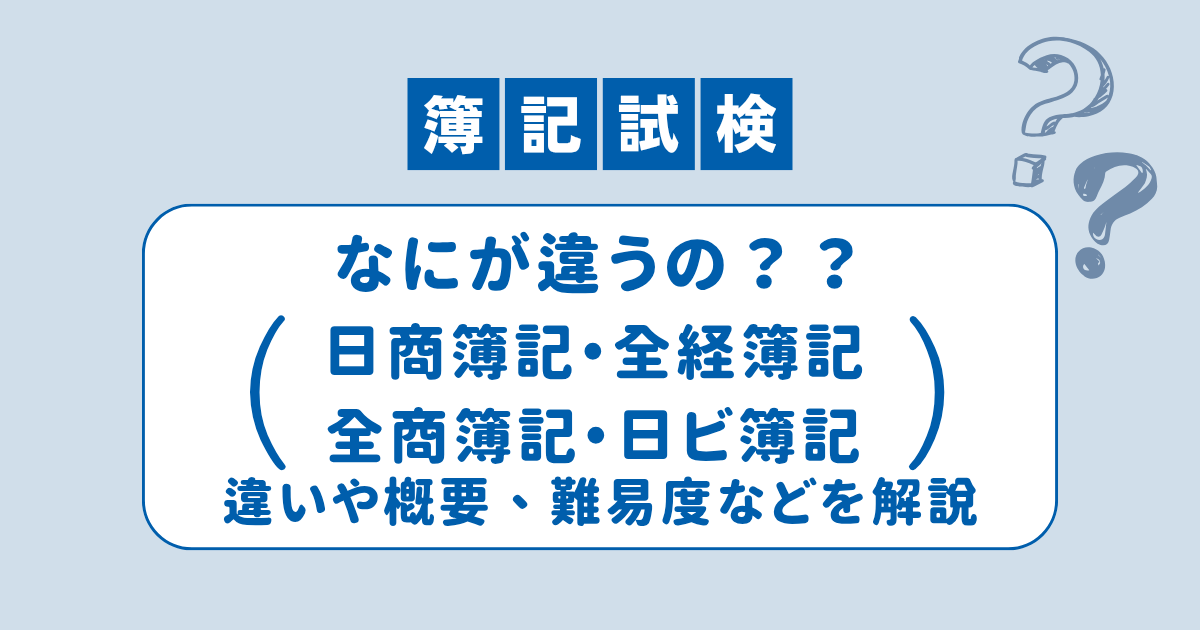※この記事にはプロモーションが含まれています。

こんなお悩みを解決します。
「簿記の資格」と言うときに、多くの人が思い浮かべるのは、「日本商工会議所」が主催する簿記試験である「日商簿記」になると思います。
簿記の資格には、「日商簿記」以外にも、「全経簿記」、「全商簿記」、「日ビ簿記」などがありますが、何が違うのでしょうか?
本記事では、簿記の資格の違いについて解説していきます。
本記事の内容は
記事の内容
になります。
それぞれの検定試験の違いや内容、難易度、合格率などについても解説していきます。

簿記検定の種類

「簿記の資格」と言うときに、多くの人が思い浮かべるのは、「日本商工会議所」が主催する簿記試験である「日商簿記」の資格になると思います。
資格の人気ランキングや、受験者数ランキングの上位に出てくるのも「日商簿記」になります。
簿記検定には、「日商簿記」以外にも、「全経簿記」、「全商簿記」、「日ビ簿記」があり、主な違いとしては、主催団体や受験者層の違いが挙げられます。
ここからは、それぞれの簿記検定について解説していきます。
日商簿記
日商簿記検定は、日本商工会議所が主催する簿記試験になります。
いくつかある簿記検定の中で最も知名度が高く、受験者層も幅広いため、年間約48万人(※)が受験している検定です。
※日本商工会議所の公表している受験者データから2023年4月〜2024年3月までの統一試験、CBT試験(1級から3級)の受験者数を集計 日本商工会議所HP
試験について
試験は、1級、2級、3級がメジャーですが、初めて簿記や原価計算を学ぶ人用に簿記初級、原価計算初級もあります。
試験範囲としては、3級は商業簿記だけですが、2級では、商業簿記に加えて工業簿記も試験範囲に入ります。
また、1級では、商業簿記と工業簿記に加えて、会計学と原価計算も試験科目に入ってきます。
合格基準
各級とも合格基準は、100点満点中の70%になります。
ただし、1級には足切りラインがあり、全科目で40%以上とりながら、全体でも70%以上の得点が合格の条件です。
1級は、各科目25点満点ですので、例えば、科目A〜Cが25点、Dが9点だった場合、合計は84点で合格ラインを超えていますが、科目Dが40%(25点×40%=10点)点に届いていないため、不合格になります。
簿記1級に合格すると税理士試験の税法の受験資格を得ることもできます。
税理士試験(税法)の受験資格の例
- 日本商工会議所主催の簿記検定試験1級合格者
- 全国経理教育協会主催の簿記能力検定試験上級合格者
- 大学、短大又は高等専門学校を卒業した者で、社会科学に属する科目を1科目以上履修した者
など
受験料について
受験料は、1級が8,800円、2級は5,500円、3級は3,300円、初級の簿記と原価計算は2,200円になります。
なお、2級、3級は、紙の試験ではなく、ネット試験を選択することもできますが、ネット試験で受験する場合には、受験料と別で事務手数料として550円かかります。
| 統一試験 (紙) | ネット試験 | |
| 1級 | 8,800円 | ― |
| 2級 | 5,500円 | 6,050円 |
| 3級 | 3,300円 | 3,850円 |
| 初級 | ― | 2,750円 |
この後で紹介する全経簿記、全商簿記、日ビ簿記は、科目ごとの受験ができますが、日商簿記は科目ごとの受験はできず、まとめて受験する必要があります。
合格率について
合格率は実施回によってばらつきがありますが、直近3年間の合格率の平均は、1級が12.7%、2級が21.7%(ネット試験は36.3%)、3級が35.6%(同39.0%)、簿記初級が62.0%、原価計算初級が90.0%です。
当記事執筆時点で確認した直近の合格率は、1級が15.1%、2級が20.9%(ネット試験は36.9%)、3級が28.7%(同39.1%)、簿記初級が60.0%、原価計算初級が90.0%でした。
| 3年平均 | 直近 | |
| 1級 | 12.7% | 15.1% |
| 2級 | 21.7% (36.3%) | 20.9% (36.9%) |
| 3級 | 35.6% (39.0%) | 28.7% (39.1%) |
| 簿記初級 | 62.0% | 60.0% |
| 原価計算初級 | 90.0% | 90.0% |
※括弧内はネット試験の合格率
※2022/6/12施行の第161回試験から2024/11/17施行の第168回試験までの平均合格率および2024/11/17施行の第168回試験の合格率(ネット試験は2022から2024年度の平均)
出典:日本商工会議所HP 受験者データ
全経簿記
全経簿記は全国経理教育協会が主催している簿記検定で、経理や会計の専門学校に通う学生向けの資格試験です。
全国経理教育協会を略して「全経簿記」と呼ばれることがありますが、正式名称は「簿記能力検定試験」になります。
学生向けの試験であり、日商簿記と比べると知名度は落ちますが、全経上級は日商簿記1級と同程度の難易度のため、日商簿記1級とあわせて受験する人もいます。
また、上級に合格すると日商簿記1級と同じく税理士試験の受験資格を得ることができますので、税理士試験のために受験する人もいます。
試験について
試験験は、上級、1級、2級、3級、基礎簿記会計の5段階です。
難易度は、全経上級が日商簿記の1級相当、全経1級が日商簿記2級相当と、日商簿記と比べて級が1つずつずれるイメージです。
1級の商業簿記・財務会計(商財)と原価計算・管理会計(原管)、2級の商業簿記(商簿)と工業簿記(工簿)は、別々に受験できますが、それぞれの級の取得には両方の科目に合格しなければなりません。
なお、以前は1級の科目合格の有効期限は4回以内(1年以内)でしたが、今は回数制限が撤廃されていますので、余裕をもって受験できます。
合格基準
各級、各科目とも合格点は、100点満点中の70点になります。
ただし、上級には足切りラインがあり、全科目で40点以上とりながら、合計で280点以上の得点が合格の条件です。
例えば、科目A〜Cが100点、Dが39点だった場合、合計は339点で合格ラインを超えていますが、科目Dが40点に届いていないため、不合格になります。
受験料について
受験料は、上級が8,700円、1級は1科目あたり3,500円、2級は科目あたり3,100円、3級は2,900円、基礎簿記会計が1,900円になります。
1級と2級は、2つの科目に合格する必要があるため、合格までには1級は7,000円、2級は6,200円かかります。
また、2級、3級、基礎簿記会計は、紙の試験ではなく、ネット試験を選択することもできます。
ネット試験で受験する場合には、受験料に追加で1,200円が事務手数料としてかかります。
| ペーパー試験 | ネット試験 | |
| 上級 | 8,700円 | ― |
| 1級 | 3,500円×2科目 | ― |
| 2級 | 3,100円×2科目 | 4,300円×2科目 |
| 3級 | 2,900円 | 4,100円 |
| 基礎簿記会計 | 1,900円 | 3,100円 |
合格率について
合格率は実施回によってばらつきがありますが、直近3年間の合格率の平均は、上級が13.9%、1級商財が40.1%、1級原管が58.2%、2級商簿が51.9%、2級工簿が80.1%、3級が63.3%、基礎が73.1%です。
当記事執筆時点で確認した直近の合格率は、上級が14.4%、1級商財が19.8%、1級原管が59.7%、2級商簿が46.8%、2級工簿が82.0%、3級が48.5%、基礎が66.2%でした。
| 3年平均 | 直近 | |
| 上級 | 13.9% | 14.4% |
| 1級(商財) | 40.1% | 19.8% |
| 1級(原管) | 58.2% | 59.7% |
| 2級(商簿) | 51.9% | 46.8% |
| 2級(工簿) | 80.1% | 82.0% |
| 3級 | 63.3% | 48.5% |
| 基礎簿記会計 | 73.1% | 66.2% |
※2022/5/29施行の第206回試験から2025/2/16施行の第217回試験までの平均合格率および2025/2/16施行の第217回試験の合格率
出典:全国経理教育協会HP 受験データ・合格率
全商簿記
全商簿記検定は、全国商業高等学校協会が主催している簿記検定で、主に商業高校の生徒が受験する資格試験です。
全国商業高等学校協会を略して「全商簿記」と呼ばれることもありますが、正式名称は「簿記実務検定試験」になります。
商業高校の生徒が授業で習う内容であり、高校で使用している教科書に沿った問題が出題されます。
試験について
試験は、1級、2級、3級の3段階ですが、日商簿記よりも難易度は低めで、日商簿記の2級が全商簿記の1級、日商簿記の3級が全商簿記の2級相当と級が1つ変わるイメージです。
1級の会計と原価計算は、別々に受験できますが、1級の取得には両方の科目に合格しなければなりません。
合格点は、各級、各科目とも100点満点中の70点になります。
受験料について
受験料は、それぞれ1,300円で、1級は会計と原価計算の受験が必要なため、合格までには1級は2,600円かかります。2級と3級は商業簿記の内容だけのため1,300円です。
ちなみに、受験資格はなく、高校生以外も受験可能です。
Q.高校生以外でも検定試験を受験することは可能ですか。
A.受験資格は特にございません。どなたでもご受験していただくことが可能です。
合格率について
合格率は実施回によってばらつきがありますが、直近3年間の合格率の平均は、1級会計が39.3%、1級原価計算が40.8%、2級が47.9%、3級が70.4%です。
当記事執筆時点で確認した直近の合格率は、1級会計が41.8%、1級原価計算が46.6%、2級が51.7%、3級が74.3%でした。
| 3年平均 | 直近 | |
| 1級会計 | 39.3% | 41.8% |
| 1級原価計算 | 40.8% | 46.6% |
| 2級 | 47.9% | 51.7% |
| 3級 | 70.4% | 74.3% |
※2022/6/26実施の第92回試験から2025/1/26実施の第99回試験までの平均合格率および2025/1/26実施の第99回試験の合格率
出典:全国商業高等学校協会HP 統計資料
日ビ簿記
日ビ簿記は、日本ビジネス技能検定協会が主催している簿記検定で、社会人向けの試験です。
日本ビジネス技能検定協会の簿記検定のため「日ビ簿記検定」と呼ばれることが多いです。
試験について
試験のレベルは、1級、2級、3級の3段階になっており、各級の難易度は日商簿記と同程度です。
1級の商業簿記・財務会計と原価計算・管理会計、2級の商業簿記と工業簿記は別々に受験することができますが、両方の科目に合格しなければ、その級に合格したことにはなりません。
1科目のみ合格した場合には、受験日から2年間有効の認定証書が発行されます。
受験日から2年以内にもう片方の科目も合格しましょう。
なお、各級、各科目とも合格点は、100点満点中の70点になります。
受験料について
受験料は、1級は各科目2,530円、2級は各科目1,980円のため、合格までには1級は5,060円、2級は3,960円かかります。3級は商業簿記だけのため1,980円です。
一般財団法人日本ビジネス技能検定協会HP「検定試験について|簿記能力検定試験」
ここまでのまとめ
日商簿記、全経簿記、全商簿記、日ビ簿記の違いをまとめると、以下の通りです。
| 日商簿記 | 全経簿記 | 全商簿記 | 日ビ簿記 | ||
| 主催団体 | 日本商工会議所 | 公益社団法人全国経理教育協会 | 全国商業高等学校協会 | 日本ビジネス技能検定協会 | |
| 主な受験者 | 学生から社会人まで幅広く | 経理や会計の専門学校に通う学生 | 商業高校の生徒 | 社会人 | |
| 級 | 5区分(1級、2級、3級、簿記初級、原価計算初級) | 5区分(上級、1級、2級、3級、基礎簿記会計) | 3区分(1級、2級、3級) | 3区分(1級、2級、3級) | |
| 科目ごとの受験 | 不可 | 1級と2級は科目ごとに受験可能(※1) | 1級は科目ごとに受験可能(※2) | 1級と2級は科目ごとに受験可能(※1) | |
| 受験形式 | 1級は紙試験、級と3級はネット試験も選択可能 、基礎はネット試験 |
上級と1級は紙試験、2級と3級はネット試験も選択可能 | 紙試験のみ | 1級は紙試験、2級と3級はネット試験 | |
| 税理士の受験資格 | 1級合計で受験資格 | 上級合格で受験資格 | なし | なし | |
| 受験料 | 上級 | ― | 8,700円 | ― | ― |
| 1級 | 8,800円 | 各3,500円 | 各1,300円 | 各2,530円 | |
| 2級 | 5,500円(ネット試験は+550円) | 各3,100円(ネット試験は+1,200円) | 1,300円 | 各1,980円 | |
| 3級 | 3,300円(ネット試験は+550円) | 2,900円(ネット試験は+1,200円) | 1,300円 | 1,980円 | |
| 初級 | 各2,200円 | 1,900円(ネット試験は+1,200円) | ― | ― | |
| 合格率 | 上級 | ― | 13.9% | ― | ― |
| 1級 | 12.7% | 商財40.1% | 会計39.3% | 非公開 | |
| 原管58.2% | 原計40.8% | ||||
| 2級 | 21.7%(ネット試験は36.3%) | 商簿51.9% | 47.9% | ||
| 工簿80.1% | |||||
| 3級 | 35.6%(ネット試験は39.0%) | 63.3% | 70.4% | ||
| 初級 | 簿記62.0% | 73.1% | ― | ― | |
| 原価計算90.0% | |||||
(※1)会計と原価計算の2科目
(※2)1級…商業簿記・財務会計、原価計算・管理会計の2科目
2級…商業簿記、工業簿記の2科目
(※3)
日商簿記:2022/6/12施行の第161回試験から2024/11/17施行の第168回試験までの平均合格率
出典:日本商工会議所HP 受験者データ
全経簿記:2022/5/29施行の第206回試験から2025/2/16施行の第217回試験までの平均合格率
出典:全国経理教育協会HP 受験データ・合格率
全商簿記:2022/6/26実施の第92回試験から2025/1/26実施の第99回試験までの平均合格率
出典:全国商業高等学校協会HP 統計資料
参考程度ですが、試験の内容から難易度を横並びで比較すると、以下のような感じになります。
| 難易度 | 日商簿記 | 全経簿記 | 全商簿記 | 日ビ簿記 |
| 高 | 1級 | 上級 | ー | 1級 |
| 2級 | 1級 | 1級 | 2級 | |
| 3級 | 2級 | 2級 | 3級 | |
| 簿記初級/原価計算初級 | 3級 | 3級 | ー | |
| 低 | ー | 基礎簿記会計 | ー | ー |
その他、建設業での経理にフォーカスした「建設業経理検定」など、業界特有の会計処理を扱った検定もあります。
日商簿記検定について

ここからは、4つの資格の中で知名度が高く、ビジネスや就活でも役に立つ「日商簿記」について、もう少し詳しく解説していきます。
3級
日商簿記3級では、すべての企業で共通となる基礎的な内容を学びます。
試験は、商業簿記のみで、商品の仕入れと販売を行っている小規模な会社の日々のお金のやり取りを記録して、決算書を作成するまでの知識を問われます。
仕訳パターンは多くなく、覚える内容は少なめですが、簿記のルールなど今後につながる大切な内容が多いです。
試験について
試験時間は60分で大問3つに答える試験となり、試験内容は以下の通りです。
| 内容 | 配点 | |
| 1 | 仕訳(15題以内) | 45点 |
| 2 | 補助簿、勘定記入など | 20点 |
| 3 | 試算表や財務諸表の作成 | 35点 |
日商簿記検定を受験する人は、3級から始める人が多く、統一試験とネット試験合計で、年間20万人以上が受験しています。
-
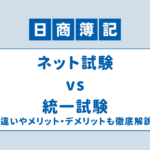
-
参考【初学者必見!】日商簿記検定のネット試験と統一試験を徹底比較
続きを見る

なお、簿記3級のレベルは、商工会議所のHPにおいて以下の通り記載されています。
業種・職種にかかわらずビジネスパーソンが身に付けておくべき「必須の基本知識」として、多くの企業から評価される資格。
基本的な商業簿記を修得し、小規模企業における企業活動や会計実務を踏まえ、経理関連書類の適切な処理を行うために求められるレベル。
簿記3級の詳細は『【日商簿記3級】試験の概要や取得のメリット、勉強方法などを解説』でまとめていますので、あわせてご覧ください。
-
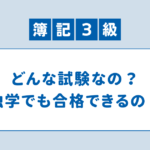
-
参考【日商簿記3級】試験の概要や取得のメリット、勉強方法などを解説
続きを見る
2級
日商簿記2級では、製造業の会社の経理や、子会社や本店支店の概念がある中規模な会社の経理で役立つ内容を学びます。
2級からは、3級では範囲外だった工業簿記が出題されるようになります。
また、商業簿記は、3級の知識を前提に範囲が広がり、内容も深くなります。
勉強する範囲が、かなり広がりますので、勉強時間は300時間以上必要と言われています。
試験について
試験は、商業簿記と工業簿記になります。
試験時間は90分で大問5つに答える試験となり、試験内容は以下の通りです。
| 内容 | 配点 | |
| 1 | 商業簿記に関する仕訳5問 | 20点 |
| 2 | 個別問題、勘定記入、連結会計など | 20点 |
| 3 | PL,BS、本支店会計などの個別決算 | 20点 |
| 4 | 仕訳3問と個別原価計算、標準原価計算などから1問 | 28点 |
| 5 | 標準原価計算、直接原価計算、CVP分析 | 12点 |
なお、簿記2級のレベルは、商工会議所のHPにおいて以下の通り記載されています。
経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ。
高度な商業簿記・工業簿記(原価計算を含む)を修得し、財務諸表の数字から経営内容を把握できるなど、企業活動や会計実務を踏まえ適切な処理や分析を行うために求められるレベル。
簿記2級の詳細は『【日商簿記2級】試験の概要や取得のメリット、勉強方法などを解説』でまとめていますので、よろしければご覧ください。
-
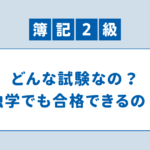
-
参考【日商簿記2級】試験の概要や取得のメリット、勉強方法などを解説
続きを見る
1級
日商簿記1級では、海外も含め子会社があるような大規模な会社の経理にも対応できる内容を学びます。
また、意思決定や収益性の分析なども試験範囲になるため、経理責任者が行うことをやるイメージです。
2級までで学んだ商業簿記、工業簿記については学習範囲がさらに広くなり、内容も複雑になります。
また、新しく会計学と原価計算も試験範囲に入ってくるため、勉強時間は600時間以上必要と言われています。
試験について
試験は、商業簿記と工業簿記に加え、会計学と原価計算が増えます。
試験時間も長くなり、商業簿記と会計学で90分、休憩を挟んで、工業簿記と原価計算で90分の合計180分の試験になります。
試験内容は広すぎるのでまとめ切れませんが、以下のような問題が出ます。
| 内容 | 配点 | |
| 商業簿記 | 損益計算書、貸借対照表、本支店や連結財務諸表の作成の総合問題など | 25点 |
| 会計学 | 理論問題と計算問題 | 25点 |
| 工業簿記 | 製品原価計算(標準原価計算など)や財務諸表の作成など | 25点 |
| 原価計算 | 管理会計を中心とした計算問題など(意思決定会計など) | 25点 |
なお、簿記1級のレベルは、商工会議所のHPにおいて以下の通り記載されています。
極めて高度な商業簿記・会計学・工業簿記・原価計算を修得し、会計基準や会社法、財務諸表等規則などの企業会計に関する法規を踏まえて、経営管理や経営分析を行うために求められるレベル。
合格すると税理士試験の受験資格が得られる。公認会計士、税理士などの国家資格への登竜門。
日商簿記1級に合格すると、税理士試験の税法科目の受験資格が得られます。
簿記1級は、過去問が商工会議所のHPで公開されています。商工会議所HP 1級過去問題


勉強の方法

どの簿記検定でも同じですが、勉強方法としては、以下の3つが考えられます。
- 市販のテキストで独学
- 通信やオンラインの講座を受講
- 通学の講座を受講
安く済ませるなら独学ですが、合格レベルに達するまで時間がかかります。
逆に、通学や通信の講座であれば、独学よりはお金がかかりますが、プロの講師に教えてもらえるため、合格レベルまで短い時間で到達できます。
どの方法で勉強するかは、資格取得や簿記を理解するまでにかけられる時間との兼ね合いで選択すると良いと思います。
独学と資格スクールの利用に関しては、『【簿記1〜3級】簿記は独学で合格できるのか?合格率や試験範囲、勉強方法等も解説』で解説していますので、参考にどうぞ。
-

-
参考【簿記1〜3級】簿記は独学で合格できるのか?合格率や試験範囲、勉強方法等も解説
続きを見る
また、スクールを利用することにした場合、国の制度を使うことで通常よりもお得に受講する方法もあります。
こちらは『簿記講座等を最大20%オフで受講する方法(教育訓練給付制度)』でまとめていますので、よろしければこちらもご覧ください。
-
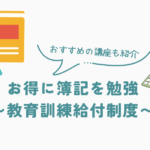
-
参考簿記講座等を最大20%オフで受講する方法(教育訓練給付制度)
続きを見る
まとめ
日商簿記、全経簿記、全商簿記、日ビ簿記の違いについて解説しました。
ご自身に合う試験を受験してもらえればと思いますが、どの試験を受けるか迷ったら、最も知名度が高く、合格後のアピール要素にもなる日商簿記を受験するのがおすすめです。
ぜひチャレンジしてみてください。