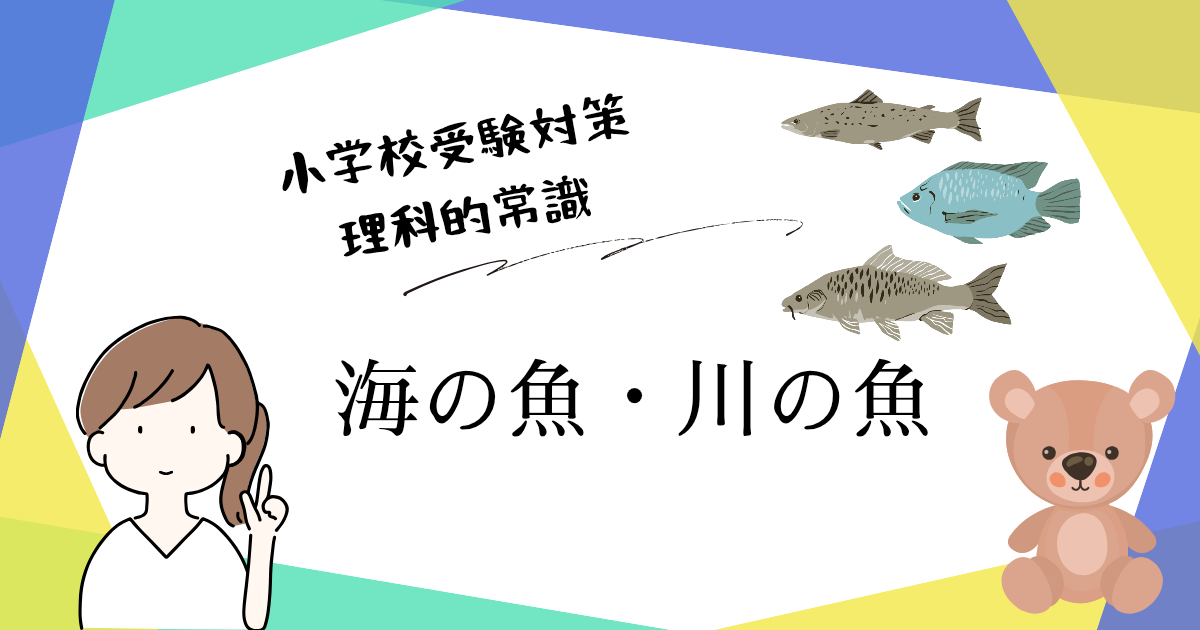※この記事にはプロモーションが含まれています。

勉強方法や、おすすめの問題集も教えてほしい!
こんなお悩みを解決します。
小学校受験の理科分野、特に「生き物」に関する問題は、お子様の興味を引きやすい反面、覚えることが多くて大変だと感じていっしゃるかもしれません。
この記事では、小学校受験で出題される可能性がある「海の魚」「川の魚」、そして「両方にすむ魚」について、具体的な一覧や効果的な学習方法などについて詳しく解説していきます。
本記事では
について解説しています。

なぜ「生き物のすむ場所」が重要なのか
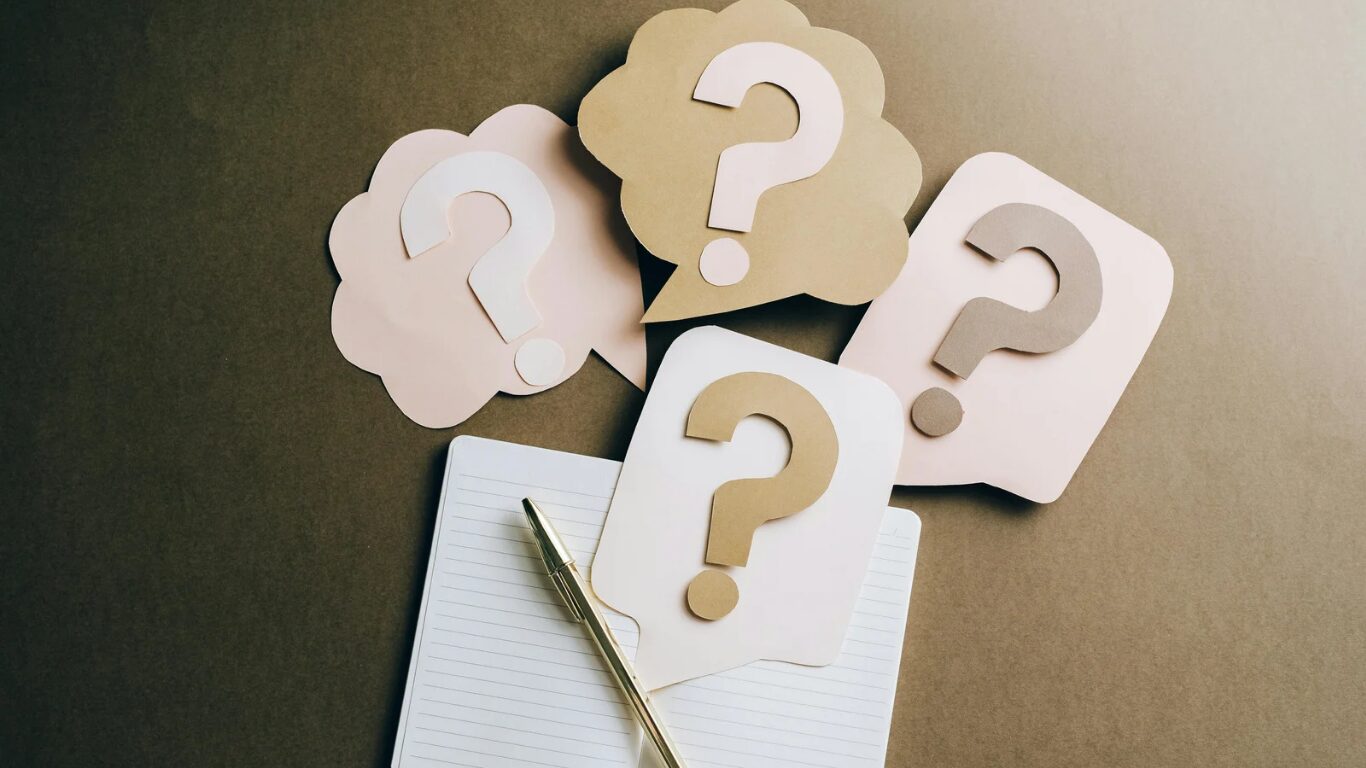
小学校受験で問われる「理科的常識」は、机の上だけで完結する、単なる暗記ではなく、お子様の「観察力」や「環境への理解」を試す、とても大切な分野です。
私たちの身の回りにある自然や環境に、どれだけ関心を持っているかという「好奇心」や「観察眼」が試されています。
「魚」というテーマも同じです。
単なる丸暗記ではなく、「なぜそこにすんでいるのか」を少し意識するだけで、お子様の学びはぐっと深まります。
どんな問題が出題されるのか

小学校受験における「水の生き物」に関連したペーパー問題では、例えば、以下のような出題が考えられます。
仲間分け
魚に限らず、よく出題される形式として、「仲間分け」があります。
たとえば、
例題
マグロ、メダカ、カエル、サケ、イルカの絵を見ながら、「この中で、海にだけすんでいる生き物に〇(まる)をつけましょう」
という問題です。
答えは、マグロとイルカになります。
ポイントは、メダカ(川)、カエル(川や池)、サケ(両方)を正しく区別できるかと、「魚」ではなく「生き物」と聞かれているため、イルカ(哺乳類)も海にすむ仲間として選ぶ必要があるということです。
この問題が「海にだけいる魚を選びましょう」であれば、答えはマグロだけになります。
仲間外れ
次は仲間外れです。
仲間外れを選ぶ形式もよく出題されるパターンの問題です。
たとえば
例題
サンマ、タイ、マグロ、メダカの絵を見ながら、「この中で、すんでいる場所が違う生き物に〇(まる)をつけましょう」
という問題です。
答えは、メダカになります。
ポイント、サンマ、タイ、マグロは「海」にすむ仲間、メダカだけが「川」にすむ仲間であることを、絵から判断できるかになります。
小学校受験で覚えておきたい魚の一覧

問題に答えるには、海と川や池にすむ生き物かどうかと、魚なのか、魚以外なのかを把握しておく必要があります。
そこで、ここからは、海の魚、川の魚、両方で生きる魚について解説していきます。
なお、魚の特徴は以下の通りですので、ご確認ください。
- 卵から生まれる
- エラで呼吸をする
- 体がウロコで覆われている
- ヒレがある
- 水の中で生きる
「海の魚」一覧
まずは、海にすんでいる魚たちです。
私たちの食卓にもよく並ぶ、おなじみの魚が多いのが特徴です。
お子様が食べたことのある魚や、水族館で見たことのある魚から覚えるとスムーズです。
できれば覚えておきたい海の魚
| 名前 | 特徴 |
| マグロ | 広い海を速く泳ぐ、大きなお魚です。お寿司や刺身でおなじみです。 |
| サンマ | 秋の味覚の代表です。「秋になるとおいしくなるお魚は?」という季節の問題でも登場します。細くて銀色に光る体が特徴です。 |
| タイ | 「おめでたい」時に食べられる、赤くてきれいなお魚です。 |
| フグ | 敵に襲われると、体をぷうっと膨らませます。お腹に毒があることでも有名です。 |
| サメ | 海の大きなハンターとして知られています。水族館でも人気者です。 |
| アンコウ | 深海にすむ、ユニークな形のお魚です。 |
| マンボウ | とても変わった形をしています。水族館でゆったりと泳ぐ姿が印象的です。 |
| タツノオトシゴ | 「竜」のような形をした小さなお魚です。 |
魚ではないけれど海にすむ仲間たち
受験では、「海の生き物」という大きなくくりで問われることもあります。
以下の生き物は「魚」ではありませんが、海にすんでいる仲間として一緒に覚えておくと良いです。
| 名前 | 特徴 |
| イカ・タコ | 足がたくさんある生き物です。うろこがなく、えらではなく皮ふやえらに似た器官で呼吸します。 |
| エビ・カニ | 固い殻で覆われています。脚がたくさんあります。 |
| クジラ・イルカ | 海にすんでいますが、私たちと同じ「哺乳類」です。卵ではなく、赤ちゃんを産み、お乳をあげて育てます。 |
| ラッコ・アザラシ・アシカ | |
| ウニ・ヒトデ | 磯遊びなどで見かけることがあります。 |
| クラゲ | プカプカと水に浮かんでいます。うろこも骨もなく、体のほとんどが水です。 |
改めてですが、魚の特徴は以下のとおりです。
特徴に当てはめて考えるとわかりやすいと思います。
- 卵から生まれる
- エラで呼吸をする
- 体がウロコで覆われている
- ヒレがある
- 水の中で生きる
「川の魚」一覧
次に、川や池(淡水)にすんでいる魚たちです。
海のお魚に比べると、少し地味な印象かもしれませんが、私たちにとって身近な生き物です。
覚えておきたい川の魚
| 名前 | 特徴 |
| メダカ | 日本の小さな小川や田んぼによくすんでいます。 |
| ドジョウ | 底の泥の中にすんでいます。細長い体と口のひげが特徴です。 |
| ナマズ | 大きな口と長いひげが特徴的な、川の底にすむお魚です。 |
余裕があれば覚えたい川の魚
| 名前 | 特徴 |
| イワナ・ヤマメ | とてもきれいな水が流れる、川の上流(山奥)にすんでいます。体にきれいな模様があります。 |
| ニジマス | 釣り堀などで人気のお魚です。 |
魚でないけれど川や池にすむ仲間たち
こちらも「川や池の魚」ではなく、「川や池の生き物」という大きなくくりで問われることもあります。
以下の生き物は「魚」ではありませんが、川や池にすんでいる仲間として一緒に覚えておくと万全です。
| 名前 | 特徴 |
| ザリガニ | 川や池の底を歩いています。エビやカニと同じ甲殻類の仲間です。 |
| カエル・オタマジャクシ | 子どものオタマジャクシは水の中で暮らしますが、大人になると陸上でも生活します。 |
| カメ | 池や川で甲羅干しをしている姿を見かけます |
「海と川の両方」で生きられる魚
ここもポイントになります。
海と川、どちらか一方だけではなく、両方の環境を行き来して生きている魚たちがいます。
これらは試験で「ひっかけ問題」として出題されることもあります。
| 名前 | 生息地 | 特徴 |
| ウナギ | 生まれる場所:海 | 遠い海で生まれて、赤ちゃんのときに川にのぼってきます。そして川や池で長く暮らして大きくなります。土用の丑の日に食べることで有名です。 |
| 育つ場所:川、池 | ||
| サケ | 生まれる場所:川 | ウナギとは反対です。きれいな川で生まれ、海に行って大きく成長します。そして、大人になると自分が生まれた川に卵を産みに戻ってきます。 |
| 育つ場所:海 | ||
| アユ | 生まれる場所:川 | サケと似ています。秋に川で生まれ、冬の間は海で暮らし、春になると川をのぼってきます。 |
| 育つ場所:海(川の近く) |
おすすめの学習方法

ここまで、海と川や池にすむ生き物について紹介してきました。
では、これらの知識をどのようにお子様にインプットしていけばよいでしょうか。
ここからは、おすすめの勉強法や、おすすめの問題集について解説していきます。
日常生活や体験でインプット
ペーパー上で詰め込み学習をしても、すぐに忘れてしまいます。
ペーパー上で学習することも必要ですが、実生活で体験をすることで記憶は「生きた知識」へと変わります。
覚えるためのテクニックがある分野ではないため、日々の生活の中等で、少しずつ知識を増やしていくことが大切です。
1.食卓での会話
食卓での会話は最も手軽な方法です。
食卓に魚料理が出たら、絶好のチャンスです。
「今日はサンマの塩焼きだね。サンマは海と川、どっちのお魚だったかな?」
このように、日常の会話にクイズとして取り入れることで、お子様は楽しく学習できます。
2.お買い物での学習
スーパーマーケットの「お魚コーナー」は、素晴らしい学びの場です。
「タイが売っているね。これは海だね」
「サケはどっちだったっけ?」
と、本物の魚を見ながら確認することができます。
3.水族館や川遊び、磯遊び
機会があれば、「本物」を見に連れて行ってあげてください。
水族館では、「ここは海の生き物のお部屋だね」「こっちは川の魚のコーナーだね」と、水槽の環境ごとに意識して観察します。
川遊びでメダカやオタマジャクシ、ザリガニを見つける体験、磯遊びをすることも記憶として残るでしょう。
図鑑や絵本でインプット
ペーパー問題の白黒の絵だけでは、魚の特徴はなかなかつかめません。
そこで、写真や精密なイラストが載っている「図鑑」を活用してみてください。
図鑑を見ながら、「このお魚は、縞模様があるね」「こっちは平べったいね」「どんなところにすんでいるかな?」と親子で会話をしてみてください。
図鑑ではなく、魚がたくさん出てくる絵本で読み聞かせをしながらでもいいと思います。
「マグロは大きいね」「メダカは小さいね」といった単純な発見も大事です。
カードを使ってインプット
カードは、ゲーム感覚で生息地や名前のクイズを出したり、仲間分けをしたりと、インプットにもアウトプットにも使えます。
市販されているカード教材を使うこともできますが、図鑑をコピーして切り抜いたり、絵を書いて自作すると、より理解が深まると思います。
ちなみに、市販のカードでおすすめなのは「くもんのカード」シリーズの『川や海の生きものカード』です。
問題集で練習する
図鑑や実際の体験、カード学習などでインプットが進んだら、「ペーパー(問題用紙)の上で正しく理解できているか」を確かめるために、市販の問題集を活用してみましょう。
「魚がすむ場所」だけをテーマにした問題集はありませんが、海や川、池の生き物を扱った問題が掲載されている問題集をご紹介します。
理英会出版「ばっちりくんドリル」シリーズ
ご紹介するのは理英会出版の問題集です。
理英会出版の「単元別ばっちりくんドリル」は、実際の入試で出題された問題を単元別に分類し、家庭学習用に発展させたドリルです。
単元ごとに「基礎編」と「応用編」があり、「基礎編」は、年中さんを対象、「応用編」は年長さん向けになっていますが、お子さまのレベルや目的に合わせて選び、取り組むことができます。
海や川、池の問題が含まれている問題集
「ばっちりくんドリル」で海や川、池の問題が含まれている問題集は、以下のものがおすすめです。
特徴
- 「海にすんでいるものに〇(まる)をつけましょう」、「海にすむものには〇(まる)、川や池にすむものには△(さんかく)をつけましょう」といった基本的な知識をストレートに問う問題が収録されている
- 魚のすむ場所以外の問題としては、卵から生まれる生き物を選ぶ問題や、成長すると何になるか(ひよこ⇛にわとり)等の問題も収録されている
学習のために買っておきたいもの

小学校受験は、一般的に1年以上の準備期間が必要になります。
そこで、最後にペーパーの学習を進めるために家にあると便利なアイテムを紹介します。
A3対応のプリンター
幼児教室で使うプリントのコピーや、テキストのコピーに使います。
コピー機がないとコンビニ等でコピーすることになり、時間とお金が余計にかかります。
小学校に入ってからも長く使えますので、家にあると便利です。
ペーパーカッター(裁断機)
テキストを印刷するために、冊子をバラバラにするために使います。
バラバラにした後は、ADF(原稿自動送り)機能があるプリンターとの組み合わせで、さらに効率的にコピーできます。
ここでは、おすすめの商品だけご紹介しましたが、詳細は『【小学校受験対策】受験準備において必要なもの、役立つもの2選』で解説していますので、あわせてご覧ください。
-
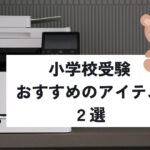
-
参考【小学校受験対策】受験準備において必要なもの、役立つもの2選
続きを見る
まとめ
海の魚、川の魚、そして両方にすむ魚。
このテーマは、覚えることが多くて難しく感じるかもしれませんが、私たちの生活や自然環境と密接に結びついた、とても大切な分野です。
大切なのは、一度にすべてを詰め込もうとしないことです。
まずはお子様の好きな魚、知っている魚から始めましょう。
皆様の取り組みを心より応援しております。