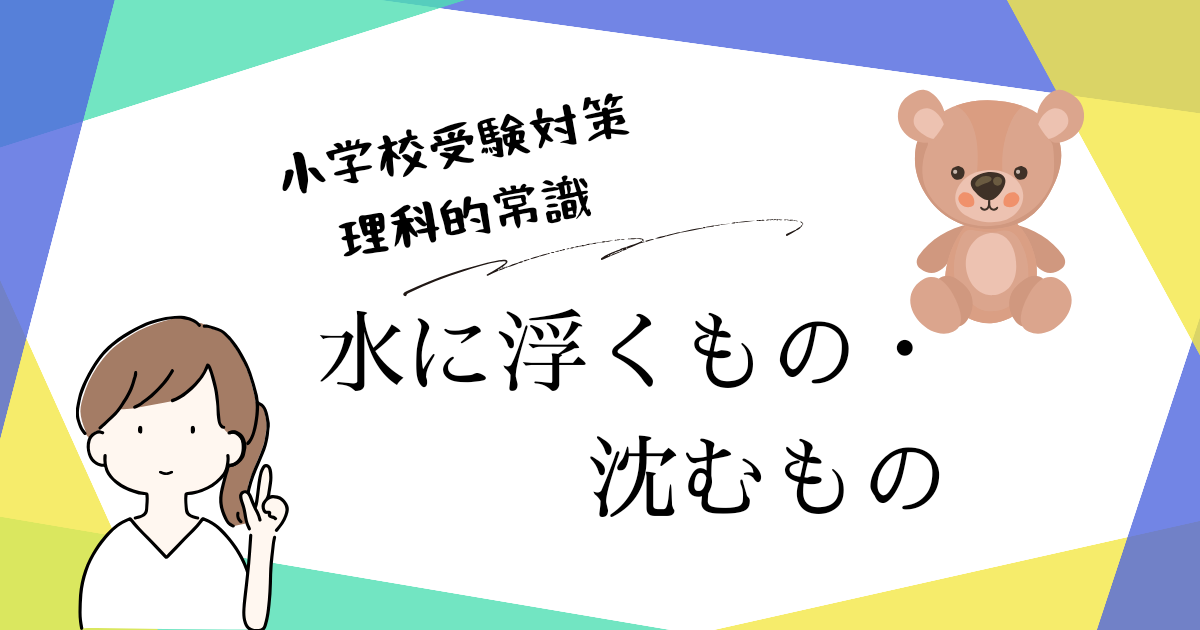※この記事にはプロモーションが含まれています。

覚えておくべきものと、おすすめの問題集も教えてほしい!
こんなお悩みを解決します。
小学校受験では、理解的常識として、水に浮くもの・沈むものが出題されます。
浮くか沈むかを覚えてしまえば終わりですが、少しでも楽に覚えられる方法や学習方法について解説していきます。
本記事では
について解説しています。

水に浮くもの、沈むものの出題

小学校受験では、理科的常識として、お題のものが「水に浮かぶか、沈むか」に関する問題が出題されます。
例えば、鉛筆、釘、クリップ、いちごの絵があり「この中で水に浮くものに丸をしましょう」といった単純な問題や、「ハサミに空気の入った風船を付けたものを水に入れるとどうなるか」といった複合問題です。
水に浮くもの・沈むものの問題は、
- 何でできているか(素材はなにか)
- どんな形か(中に空気が入っているか)
- 野菜や果物であればどこで育つか
を理解することが重要です。
このあとで、1つずつ解説していきます。
水に浮く素材・形状、沈む素材・形状
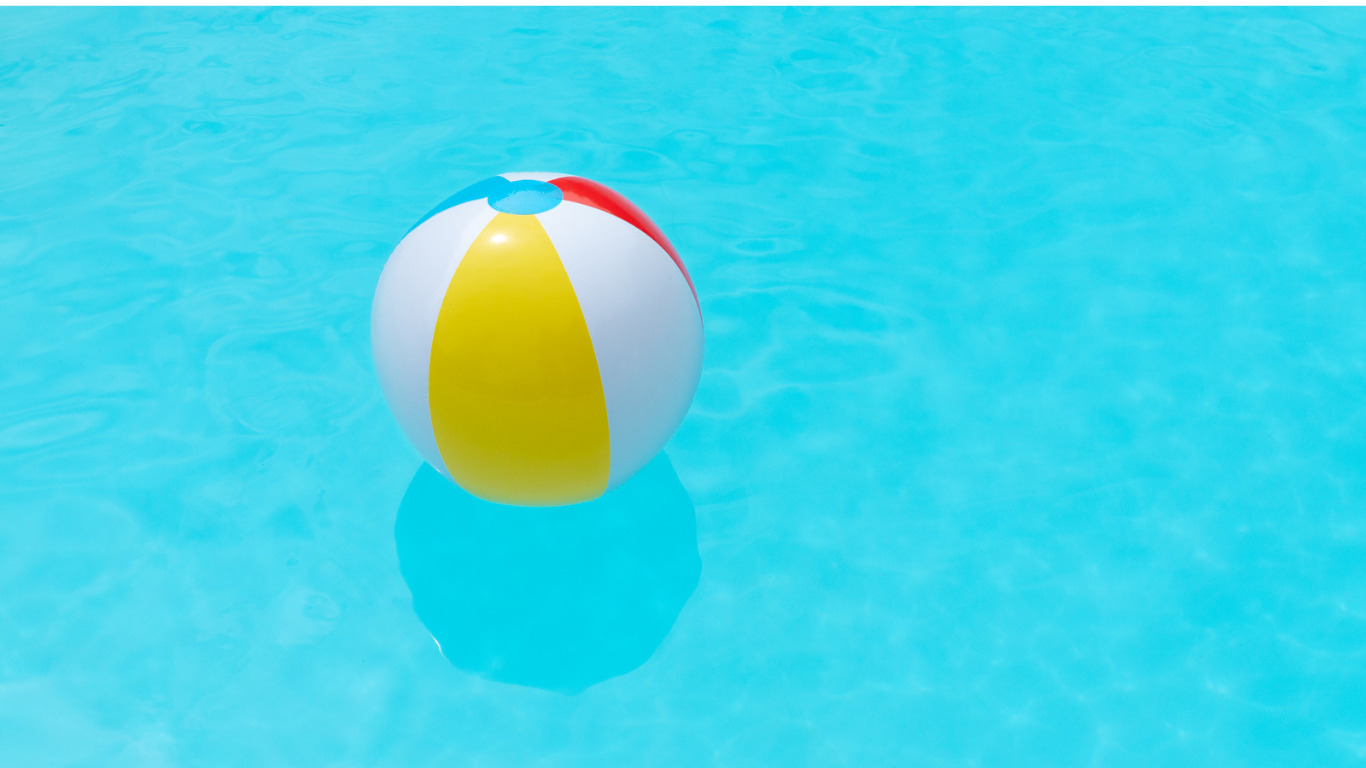
水に浮かぶか、沈むかを考えるにあたっては、その物体が何でできているか、どんな形をしているかがポイントになります。
素材
まずは、小学校受験で出題されそうなものについて、素材ごとに水に浮くもの、沈むものをまとめてみました。
| 素材 | 具体例 | |
| 水に浮く | 木 木製品 |
木の枝、葉っぱ、鉛筆、箸、まな板、積み木 など |
| 紙 | はがき、お金(1千円札、5千円札、1万円札) など |
|
| プラスチック(の仲間) | 食品トレー、スポンジ など |
|
| ゴム | ゴムボール など |
|
| 水に沈む | 金属 | くぎ、かなづち、ねじ、がびょう、はさみ、クリップ、スプーン、フォーク、電池、お金(1円、5円、10円、50円、100円、500円) など |
| ガラス | ビー玉 など |
|
| 石 | 磁石、レンガ など |
それぞれのものが何でできているかを把握することも大事ですが、実際に触ってみて、重いか軽いか、ということを経験しておけば、直感で区別できるようになると思います。
厳密には、例えば、水に浮く金属(マグネシウムやナトリウム等)もありますが、小学校受験では出題されないため「金属は水に沈む」としてまとめています。
形状
次に形状に着目して、小学校受験で出題されそうなものについて、水に浮くもの、沈むものをまとめてみました。
| 素材 | 具体例 | |
| 水が入らなければ浮く (水で満たされると沈む) |
金属 | やかん、鍋、船、空き缶 など |
| ガラス | 空きビン など |
|
| 陶器 | 茶わん など |
|
| プラスチック | ペットボトル など |
金属や陶器でも、中に空気が詰まっているものや、空洞で中に水が入っていない状態のものは浮きます。
例えば、やかん、茶わん、鍋、コップなどは、中に水が入っていなければ浮きますが、水が入ると沈みます。

水に浮く野菜、沈む野菜

次に野菜が水に浮くか、沈むかについて解説していきます。
注意
野菜と果物の区別については、いろいろな説がありますが、当記事では「木になる実を果物、木ではなく苗から育てるものを野菜」としています。
なので、スイカやメロン、いちごは野菜としています。
覚え方、考え方
まず、水に浮く野菜、水に沈む野菜の基本的な考え方です。
土の上で育つものは、水に浮く
土の中で育つものは、水に沈む
これが原則です。
例外もありますが、どこで育つかを覚えることで野菜の浮き沈みについては基本的には対応できます。
代表的な野菜と注意が必要な野菜
小学校受験で出題されそうな代表的な野菜をまとめました。
| 土の上で育つ 水に浮く |
きゅうり、かぼちゃ、きゃべつ、レタス、はくさい、なす、ピーマン、ブロッコリー、ほうれんそう、とうもろこし、しいたけ、スイカ、メロン、いちご など |
| 土の中で育つ 水に沈む |
にんじん、じゃがいも、さつまいも、かぶ、れんこん、さといも など |
なお、注意が必要な野菜は、トマトです。
熟していないトマトは水に浮きますが、熟したトマトは水に沈みます。
水に浮く果物、沈む果物

果物は木になるもので、土の上で育っているため、基本的に水に浮きます。
野菜と同様で例外はありますが、どこで育つかと例外を押さえれば対応できます。
代表的な果物と注意が必要な果物
小学校受験で出題されそうな代表的な果物についてもまとめました。
| 水に浮く | りんご、みかん、バナナ、もも、ゆず、パイナップル など |
| 水に沈む (例外) |
ぶどう、さくらんぼ、なし、かき、キウイ など |
注意が必要な果物は、ぶどう、さくらんぼ、なし、かき、キウイです。
これらは、糖度が高いため水に沈みます。
学習方法

ここまで、素材や形状、どこで育つかの観点で分類してきました。
何でできているかや、どこで育つかがわかれば回答できる問題も多いですが、子どもには、何でできているかを判断するのは難しいと思います。
ここからは、おすすめの勉強法や、おすすめの問題集について解説していきます。
実験する
ペーパー上で詰め込み学習をしても、すぐに忘れてしまいます。
そこで、水槽を用意したり、お風呂に水を張ったりして、実験するものが浮くか沈むかを予想しながら、ゲーム感覚で実験をしてみましょう。
ペーパー上で学習するだけでなく、実体験をともなった方が記憶に残ります。
また、実験のためにいろいろと用意しなくても、日々のお手伝いの中等で、水の中に入れていいものを水に入れてみて、少しずつ繰り返し経験することも大事です。
問題集で練習する
実験で学ぶだけでなく、いろいろな問題で練習することも大切です。
水に浮くか沈むかに関する問題が含まれている問題集は、以下のものがおすすめです。
理英会のばっちりくんドリル
1冊目と2冊目は、理英会から以下の2冊です。
- 『77単元別ばっちりくんドリル 身のまわりの理科(基礎編)』
- 『78単元別ばっちりくんドリル 身のまわりの理科(応用編)』
特徴
- 理英会の問題集は、基礎編と応用編に分かれており、理解度に応じて取り組むことができます。
- 全30問構成ですが、水に浮くもの、沈むものだけではなく、影のでき方や、磁石に付くもの、風向きなどの問題も含まれています。
- 応用編では、1つの物の浮き沈みだけでなく、複合問題も含まれています。
こぐま会 ひとりでとっくんシリーズ
3冊目は、こぐま会から『ひとりでとっくん54 理科的常識1』です。
特徴
- 理科的常識は、1と2の2冊にわかれていますが、理英会の問題集と異なり、基礎編と応用編には分かれていません。
- 水に浮くか沈むかだけでなく「工夫すると浮くものはどれか」という問題もあります。
- 野菜の断面や花の季節、水や鏡に映る姿、影のでき方などの問題も含まれています。

100点キッズドリル
4冊目は『100点キッズドリル 幼児のりかのじょうしき』です。
特徴
- 生き物、植物、食べ物、生活の中の物理・化学に関する様々な問題が収録されています。
- 問題ごとに「おうちのかたへ」としてミニコラムがあり、親の勉強にもなります。
- カラー印刷で取り組みやすいです。
いろいろな問題集に触れることで、違う角度からの問題にも取り組めるため、自信がつくと思います。

学習のために買っておきたいもの

小学校受験は、一般的に1年以上の準備期間が必要になります。
そこで、最後にペーパーの学習を進めるために家にあると便利なアイテムを紹介します。
A3対応のプリンター
幼児教室で使うプリントのコピーや、テキストのコピーに使います。
コピー機がないとコンビニ等でコピーすることになり、時間とお金が余計にかかります。
小学校に入ってからも長く使えますので、家にあると便利です。
ペーパーカッター(裁断機)
テキストを印刷するために、冊子をバラバラにするために使います。
バラバラにした後は、ADF(原稿自動送り)機能があるプリンターとの組み合わせで、さらに効率的にコピーできます。
ここでは、おすすめの商品だけご紹介しましたが、詳細は『【小学校受験対策】受験準備において必要なもの、役立つもの2選』で解説していますので、あわせてご覧ください。
-
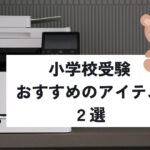
-
参考【小学校受験対策】受験準備において必要なもの、役立つもの2選
続きを見る
まとめ
小学校受験の理科的常識問題で出題される「水に浮くもの、沈むもの」と、学習方法、おすすめの問題集などについてご紹介しました。
当記事を参考に理解が進み、小学校受験で良い結果が出ることを祈っています。